



屋久島で育む
チョウたちの楽園
ここ屋久島はチョウの楽園。
それはチョウの幼虫が食べる植物(食餌植物)が多種多様であるからにほかなりません。
屋久島はその標高差から、亜熱帯の照葉樹林から亜寒帯気候の植物までが育ちます。
ツマベニチョウは、そんな屋久島の海岸部分に広がる「里」に分布しています。
ここは、照葉樹林の森の林縁部。人々の住まいにはブッソウゲ(ハイビスカス)やシコンノボタンが咲き乱れ、隣接している照葉樹林には幼虫の食草であるギョボクがたくさん育ちます。


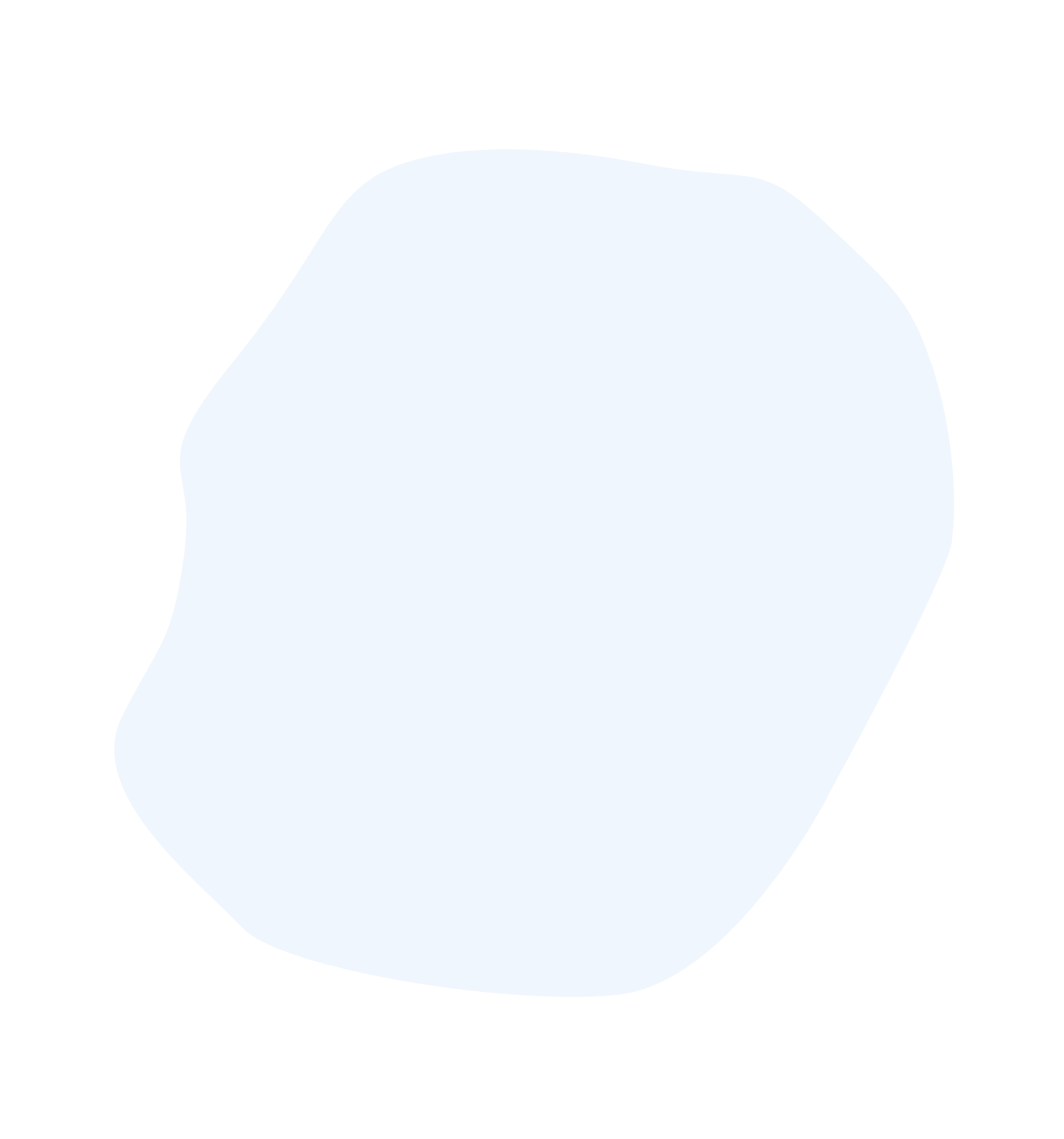

ギョボクはその名の通り、
魚を釣るための餌木(エ
ギ)、すなわちルアーとし
て利用され、漁師町での植栽とともにツマベニチョウも生息域を広げてきました。ところがプラスティックルアーの台頭によりギョボクとツマベニチョウはその数を減らしています。
そこで、ここセンバスビレッジでは2021年、この人の営みと密接に関係のあるツマベニチョウの保養施設を作りました。
 青い空、ハイビスカスの赤、森林の緑。この3色をバックに強い飛翔力で舞い上がる、白とオレンジのツマベニチョウ。
青い空、ハイビスカスの赤、森林の緑。この3色をバックに強い飛翔力で舞い上がる、白とオレンジのツマベニチョウ。
卵から幼虫、前蛹から蛹、そして成虫へ姿を変え、屋久島の四季折々の自然とともに生きる命の美しさ。ギョボクの植栽という人類の営力を自らの繁栄に利用するしたたかさ。
そんなツマベニチョウたちが命を紡ぐ物語を、みなさまとともに描いていけたらと願っております。
ABOUT tefu tefu HOUSE
tefu tefuハウスって?
ここtefu tefuハウスは、自然の息吹を感じられる特別な空間です。ここではできるだけ屋久島の環境を感じられるよう、自然に近い環境を再現しています。
ハウス内には、ツマベニチョウの幼虫の食草となるギョボクや、成虫が訪花する植物が豊富に植えられ、幼虫から成虫までの成長過程をじっくり観察することができます。ギョボクを使った餌木の展示もあるので、ぜひ手にとってみてください。
訪れる方々には、まるで自然の中にいるかのような心地よさを感じながら、ツマベニチョウの生命の美しさや人との交わりを実感していただけます。



ABOUT GREAT ORANGE TIP
ツマベニチョウって?
幸せを呼ぶ蝶 ツマベニチョウ
幸せを呼ぶ蝶 ツマベニチョウ南国の風が吹き抜けるこの土地に、白色とオレンジ色の翅を広げ、ひときわ鮮やかなチョウが舞い上がります。
その名はツマベニチョウ。彼らは温かな気候を好み、幼虫の食草であるギョボクの分布拡大とともに生息域を広げてきたと考えられています。まさにツマベニチョウは自然界の中でたくましく生き抜く生命の象徴です。
私たちのtefu tefuハウスでは、そんなツマベニチョウの美しさとたくましさを間近で感じていただけます。
 オス
オス
 メス
メス

DETAILED INFORMATION
-
呼称
-
分布
-
生態
-
食草
-
変異
学名:Hebomoia glaucippe
和名:ツマベニチョウ (褄紅蝶)
英語名:Great Orange Tip
ツマベニチョウはシロチョウ科の最大の種。英語名のOrange Tipは同じシロチョウ科のチョウ、ツマキチョウ類に使われる。よって和訳すると巨大なツマキチョウ、ということもできる。
九州南端部と南西諸島のほぼ全域。南方系のチョウで多くの亜種に分かれ、赤道をまたいで南アジアのインドヒマラヤ地域とウォーレシア(ワラセア)から南西諸島に至る亜熱帯が主たる分布地。
屋久島や種子島では昔から普通に見られる。従来から九州本土では大隅半島の佐多岬、指宿など薩摩半島南端あたりで見られていたが、近年は鹿児島市内などでも、食餌植物のギョボクがあれば卵や幼虫、蛹が見つかる。2024年現在、北限は宮崎県南郷町南郷大島。
地球温暖化傾向の続く21世紀の今日では、より冷涼な旧北区に分布の中心がある年1化※のツマキチョウ類よりも、多化性※のツマベニチョウのほうが南九州においても見る機会が多いかもしれない。
ちなみに2024年現在ツマキチョウは屋久島が南限の生息域。
※年1化:卵から成虫になるまでの過程(世代)が1年間に1度だけ見られる様式。
※多化性:1年間に世代を複数回繰り返す様式。回数に応じて年2化、年3化…と表現される。
多化性。屋久島では年4~5化。屋久島では蛹で越冬するとされているが、2023年〜2024年の記録的な暖冬化では、tefu tefuハウス内において幼虫で越冬している個体が確認された。
2009年にオーストラリアの研究チームが成虫の翅にアンボイナ(イモガイ科)と同じ毒である、ペプチド毒グラコントリファン-Mが含まれることを発見した。
成虫は、ハイビスカス(ブッソウゲ)などの大柄な花の蜜を訪れることが多いが、シコンノボタンやランタナ、サンタンカなどにも吸蜜に来る。
幼虫の食草はフウチョウソウ科のギョボク。ただし飼育下においてはアブラナ科のイヌガラシやダイコンを与えても育つ。
九州南部から与那国島にかけていくつかの変異集団が認められる。各地域ごとに明瞭に区分されるような顕著な特徴ではない。 1955年に4亜種に分けられるという報告があるが(黒澤・尾本1955)、そこまで明瞭に区別できないとの異論が多く賛同者はいなかった。
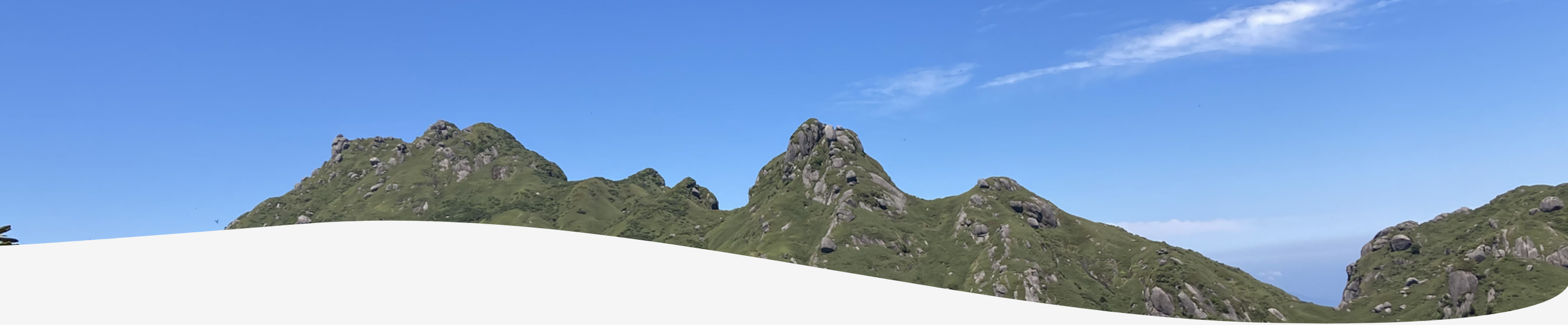
LIFE OF GREAT ORANGE TIP
ツマベニチョウの一生
ABOUT CRATAEVA RELIGIOSA FORST
食草のギョボクについて
ギョボクとは
フウチョウソウ科。屋久島では低地照葉樹林帯に多く分布。地下根茎からも萌芽する様子がうかがえる。じめっとした日当たりの悪いところで生育している。屋久島においては標高110mが分布限界とも言われている。ツマベニチョウのメスがオスよりも暗い色をしているのは、薄暗い低地
照葉樹林帯を飛び産卵するためなのであろうか。
葉型は三枚の葉が展開する三出複葉(さんしゅつふくよう)。夏頃に枝先から多数の白い花が開き、「花序」と呼ばれる花の集団を形成する。花弁は4枚。雄しべは長く突き出す。


屋久島でのギョボクについて
屋久島では古来からこのギョボクを原材料として、魚釣りの餌木(ルアー)を作っていた。筆者(竹本)が1995年に屋久島を訪れたとき、一湊集落と宮之浦集落で餌木削り1個100円のアルバイトが存在していたが、いまはもうない。屋久島で言うところのバカ木(成長が早く折れやすい木)。餌木としての使い道がなくなったこと、また従来から折れやすい性質のため、集落周辺のギョボクはどんどん伐採されている現状がある。屋久島島内の一部の地域では、ギョボクを植えツマベニチョウを呼び戻す運動を展開している。
GALLERY
ギャラリー
インスタグラムの投稿
#ナイスセンバス で投稿しよう



























